名古屋のランドマークといえば「名港トリトン」。SNSをのぞくと、ため息が出るほどカッコいい写真が並んでいますよね。
「どうやってこんな構図で撮ったんだ?」と自分の技術との差に絶望しつつも、実際に自分の足で撮影ポイントを探してみることにしました。

ただし相手は巨大建造物。全体を収めようとすると広すぎて難しく、ロケーション選びがすべてといっても過言ではありません。今回はその中でも名港中央大橋を中心に狙ってみました。
秋の気配が漂ってきたとはいえ、日中はまだまだ暑い…。汗を拭きながらのフォトウォークは、なかなかの修行でした。

名古屋で「どこで写真を撮ればいいの?」と迷っている初心者さんにも役立つように、実際に歩いた体験をまとめています。
さらに記事の最後には、撮った写真をRAW現像でどう仕上げたかのビフォーアフターも紹介しますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
目次
名港トリトンとは?名古屋港をまたぐ巨大な3つの橋

名古屋港にドーンとそびえるのが「名港トリトン」。
名前は知っていても、「実際どんな橋だっけ?」という方も多いと思います。
正体は、名古屋港に架かる3本の大橋の総称。東から順に
- 名港東大橋(赤)
- 名港中央大橋(白)
- 名港西大橋(青)
と並んでいます。遠くから眺めると赤・白・青が一直線になり、海の神「トリトン」にちなんで呼ばれるようになったそうです。
2003年に開通し、今では伊勢湾岸自動車道の一部。物流の大動脈として大型トラックがひっきりなしに走り抜ける一方で、名古屋港のシンボル的な存在として写真好きの目を引いてきました。
写真スポットとしての魅力
名港トリトンの魅力は、時間帯によってガラリと表情を変えるところ。
- 昼は青空に映える白い中央大橋
- 夕方はシルエットが美しいマジックアワー
- 夜はライトアップされて港の夜景に浮かび上がる姿
と、いつ訪れても撮りがいがあります。
ちなみに中央大橋の主塔は高さ172m。近づくと「レンズに収まらんぞ…」と苦笑いしてしまうほどのスケール感です。

撮影の難しさと楽しさ
名港トリトンは広大なエリアにまたがっているので、良い構図を得るには「どこから撮るか」がとても大事。
- 金城ふ頭側からは橋を間近に
- 空見町側からは中央大橋を正面に
- 飛島村側からは西大橋を大きく
…と立ち位置によって見え方がまったく変わります。
今回はその中でも存在感のある名港中央大橋を中心にフォトウォークしてきました。
金城ふ頭駅に到着、まずは人の多さにビビる
 ILCE-7CM2 f/8 1/200sec ISO-100 20mm
ILCE-7CM2 f/8 1/200sec ISO-100 20mm

少し寝坊して出発は9時ごろ。あおなみ線に揺られて金城ふ頭へ。
車内は子供連れや若者でぎゅうぎゅう。普段は静かな通勤電車しか乗らないので、「あれ?若者ってこんなにいたの?」と軽くカルチャーショックを受けるおじさん。
駅に着くと、なにやらイベントかコンサートがあるらしく、すでに人だかり。
「わしは橋を撮りに来ただけなのに…」と、心の中でつぶやきながら列を横目に通過します。

撮影1|リニア鉄道博物館の裏から中央大橋を狙う
 ILCE-7CM2 f/16 1/80sec ISO-100 70mm
ILCE-7CM2 f/16 1/80sec ISO-100 70mm
駅から港方面へ歩いていくと、目の前に現れるのは立ち入り禁止の看板。
「はいはい、またですか」とおじさんは肩を落とします。
名古屋港は工業地区ばかりで、沿岸部のほとんどが名古屋港管理組合の私有地となっています。
しかしここであきらめないのがフォトウォーカー魂。ぐるっと回り込んでリニア鉄道博物館の裏手まで行くと、なんと…!
しっかりと中央大橋が見えるじゃないですか。
「おお、やっと出会えたぞ」と思わず口にしてしまい、周りに人がいなくて助かりました。
ここはぜひ押さえておきたい撮影ポイントです。
撮影2|空見町に渡り名港中央大橋を狙う
次に狙うのは空見町側からの正面アングル。
でもその前に、リニア鉄道館を出てから金城橋に向かうまでにもいくつか写真が撮れるスポットがありました。





 ILCE-7CM2 f/11 1/100sec ISO-100 70mm
ILCE-7CM2 f/11 1/100sec ISO-100 70mm
金城橋を渡るとき、思った以上に距離があって「おじさん、そろそろ帰ろかな」と弱音が出そうになります。
でも頑張って渡った先にはご褒美が。
 ILCE-7CM2 f/11 1/125sec ISO-160 70mm
ILCE-7CM2 f/11 1/125sec ISO-160 70mm
名港東大橋と遠目に見える場所を発見。
名港潮見インターのループが重なって見えます。
そしてさらに探すと、中央大橋を正面から、ドーンと迫力いっぱいに撮れるスポットを発見!


 ILCE-7CM2 f/11 1/125sec ISO-100 28mm
ILCE-7CM2 f/11 1/125sec ISO-100 28mm
汗だくになった甲斐がありました。
中央大橋を撮影できるスポットはこれ以上見つけることはできませんでした。空見町からはこのあたりがベストスポットとなりそうです。





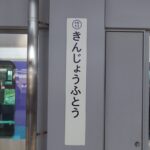














コメント